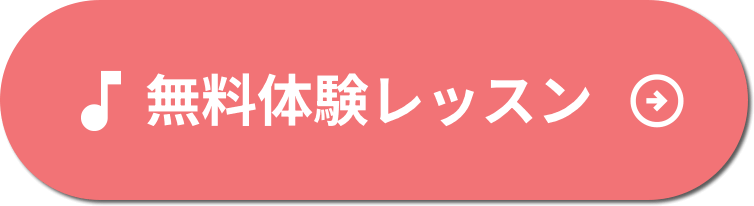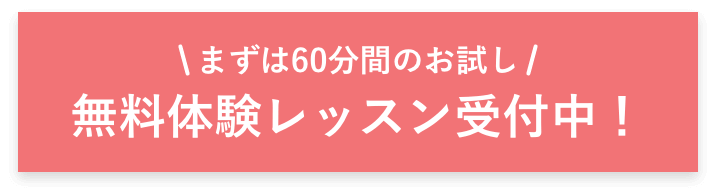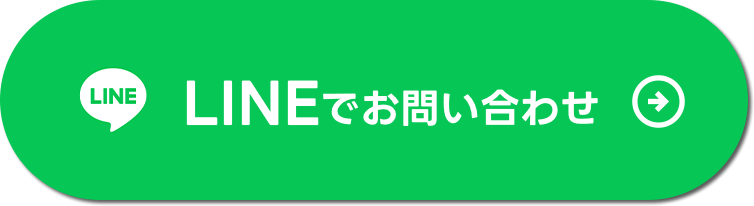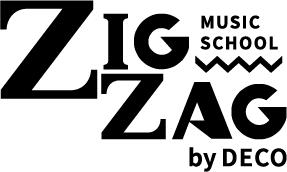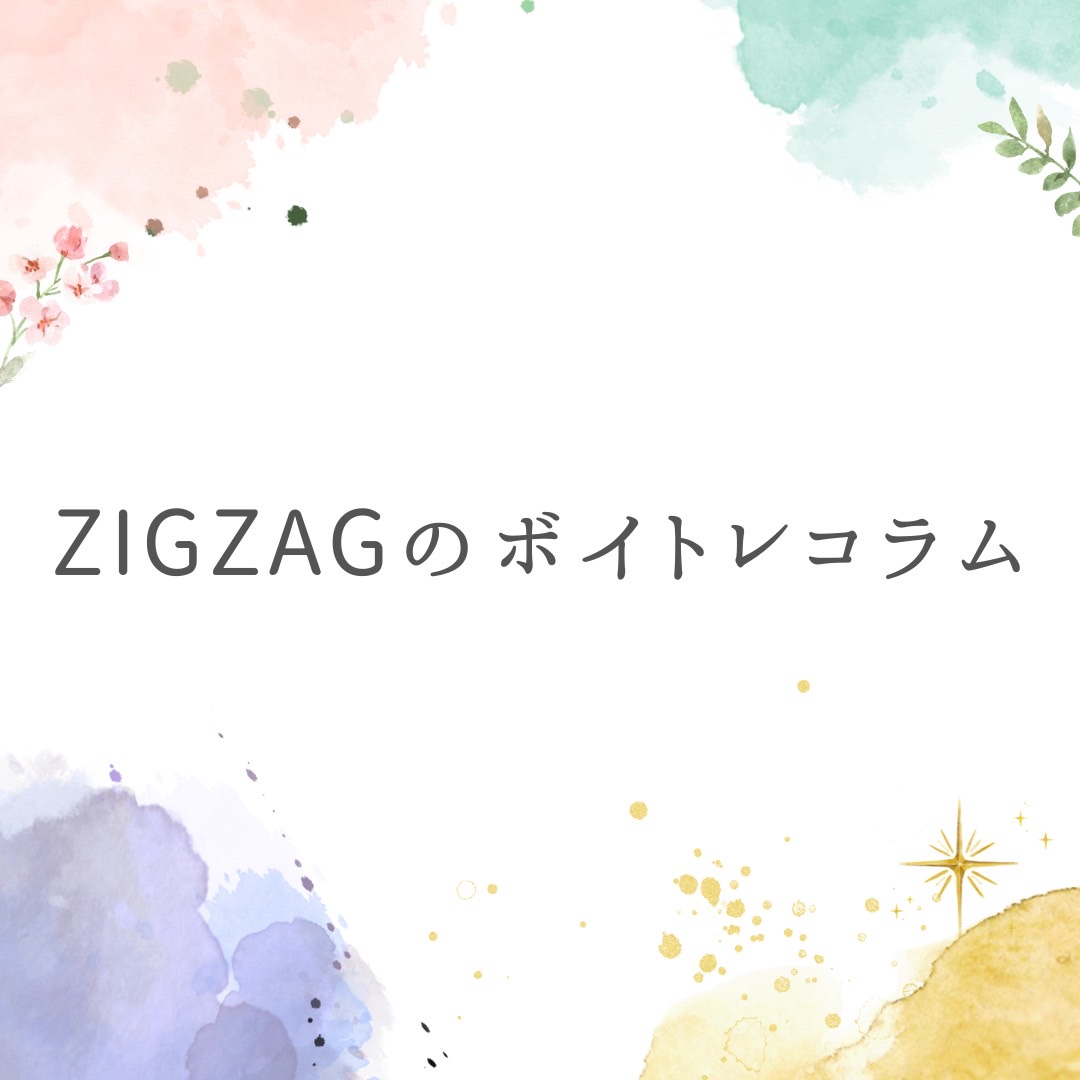紅白にも出場しいまや時の人となったtuki.さん。
その魅力と歌い方についてここでは徹底的に解説していきます。
「晩餐歌」の魅力とその背景
tuki.さんの代表曲「晩餐歌」は、リリース当初からSNSを中心に反響を集め、瞬く間に注目を浴びた一曲です。
耳に残るメロディと、儚くも芯のある歌声、そして印象的なフレーズの数々。
それらが混ざり合い、聴く人それぞれの記憶や情景を呼び起こすような、不思議な魅力を持っています。
このセクションでは、歌唱分析に入る前提として、「晩餐歌」という楽曲自体の魅力に迫ってみたいと思います。
「晩餐歌」という楽曲の印象
「晩餐歌」を初めて聴いたときにまず感じるのは、静けさと余白の存在です。
アコギを基調としたシンプルな伴奏は、まるで広い空間にぽつんとキャンドルが置かれているよう。
耳をすませて聴くほどに、そこに宿る感情の濃度が伝わってきます。
一方サビでは感情を吐き出しながらも、荒げると言うよりはむしろきれいに歌いあげることで内に秘めたものが浮かび上がってくる
その静けさがあるからこそ、かすかな揺れや言葉の抑揚がよりくっきりと浮き立ちますね。
構成とアレンジのストーリー性
「晩餐歌」の構成は非常にシンプルです。
Aメロ、Bメロ、サビからのラストで転調という王道構成で、全体に一貫した「揺るがなさ」があります。
その結果、聴き手は旋律やリズムよりも「言葉」や「声そのもの」に自然と意識が向かう構造になっています。
これは語りに近い印象を残す楽曲構成のため、tuki.さんの声にもぴったりな内容だといえるでしょう。
歌うときに押さえたいポイント
「晩餐歌」を歌おうとすると、単に音程をなぞるだけではなかなかtukiさんのニュアンスには近づけないことに気づきます。
ここでは、実際に歌う際に意識しておきたい重要なポイントについて掘り下げていきます。
息のコントロールとピッチ変化
tuki.さんは晩餐歌でウィスパーボイスと地声が絶妙に混じった声で歌っています。
息が多すぎると輪郭がぼやけ、少なすぎると硬さが目立ってしまいます。
歌う際には、息を「吐きすぎない」「語尾などで音を残しすぎない」この中間を探る意識がとても重要です。
は行などの言葉では息を多めに入れて、語尾では息を多めに吐いて歌う。
このような形で独特できれいな歌声がつくれるようになってきます。
実際歌ってみるとこの「わずかなブレ」の再現がいかに難しいかを実感するでしょう。
独特なテンポ感
もしtuki.さんが頭から終わりまで流れるように歌った場合にはどうでしょうか。
たしかにそういった構成でもいい曲かもしれません。
しかし晩餐歌にはよりその曲を独特にさせるテンポ感があります。
特に歌詞の中の「会いたくなんだよね」や「大体曖昧なんだよね」は、曲の中にスパイスをいれるようにオンビートで「置くように」発音していきます。
普通こういった儚さが際たつような声質のアーティストは、その声を活かすように流れるように歌うことが多いですが、tukiさんはこういったポップなテンポも差し込むことでまた違った印象を与えます。
このリズム感を掴むには、歌詞を一度「朗読」してみるのも有効です。
歌詞の言葉ひとつひとつに「息」と「間」を意識してのせる練習をすると、歌に自然な抑揚が生まれてきます。
声のひびき
tuki.さんの歌声は囁くようでありながら芯に太さがあります。
この声を表現するためには、ただ響く声を作るだけではなく、そのあとにその支えを外しながらも響かせていく作業が必要になってきます。
息と共鳴のバランスを保ったまま力を抜いていく、この繊細なプロセスが彼女の歌声の肝ともいえるでしょう。
印象的なフレーズとその表現法
「晩餐歌」には、リスナーの心に強く残るフレーズがいくつかあります。
ここでは、その中から特に印象的な部分をピックアップし、どのように表現すればそのニュアンスを引き出せるかを考察していきます。
「ない」からの「ちょうだい」
この曲のはじまりは、否定からはじまります。
Bメロでは
味気ないんだよね
会いたくなんだよね
君以外会いたくないんだよね
と、まさに「ないない」続きです。
ですがサビが終わるとときには、「最高のフルコースを頂戴」と、「頂戴」という最初の自分の言葉とは真逆の言葉が使われます。
こういった言葉によるギャップがまさにtuki.さんの魅力であり、tuki.さんの曲ではこういったギミックが全体を通して使われています。
こういった何気ない言葉のコントラストに注目してみると、深いテーマ性が隠れていることに気づくはずです。
どんどん増えていく数
「何十回の夜を過ごしたって」という歌詞が登場しますが、これは進むにつれてどんどん数が多くなっていきます。
何百回の夜を過ごしたって
何千回の夜を過ごしたって
何万回の夜を過ごしたって
という形です。
こうして歌が後半に行く事に募る思いが重なっていくことを表現しています。
大きな言葉のインパクトよりは、こういった積み上げが、tuki.さんの真骨頂だといえるでしょう。
Cメロでの本音
離れないで 傍に居てくれたのは
結局君一人だった
といった形で、Cメロにきてようやく素直な言葉を綴ります。
こういった形で本音をしっかりと後ろにためる演出、これもまた言葉の綴方の妙といえるでしょう。
一見よく使われる言葉のかたまりの、その全体を見据えた配置の仕方こそがtuki.さんの言葉の才能といえるかもしれません。
感情を込めるためのアプローチ
tuki.さんの歌には、決してオーバーではないのに、なぜか胸に迫る感情の波が確かに存在します。
ここでは、感情表現をするために具体的にどのような技術や意識を持てばよいかを紹介します。
AメロBメロとサビの歌い方のギャップ
AメロBメロではまさに語るように息漏れが多い歌い方をしていても、サビになると一点に響くような音で高いところまでアプローチしていきます。
これは前半の悲しみの序章というような雰囲気から、「今まさに伝えたいことをうたう」というように歌が変化していきます。
こういった歌の構成の妙でしっかりと前半に惹きつけた人の心をゆさぶります。
全体を通して感情が伝わるような構成を意識した歌い方が、tukiさんの歌には詰まっています。
共鳴する声のポジションと口の開き
また、声の響かせ方もポイントです。
tukiさんの歌い方は、胸や喉ではなく、口先〜頭蓋骨あたりに軽く共鳴させるイメージで歌われています。
そのため、口は必要以上に大きく開かず、自然体を保つことが大切。
「口の中に小さな空間を作るイメージ」で歌うと、軽やかな響きが出やすくなり、繊細な表現がしやすくなります。
余韻の残し方
前半に出てくる歌詞で「君を泣かすから」というフレーズがあります。
これを普通に「から」と発音せずに、語尾を切らずに余韻を残すように表現するのがポイントです。
語尾に息を少し多めにのせることで、感情を押しつけずに漂わせるような印象になります。
tuki.さんの歌声が持つ「さりげない切なさ」は、こうした余韻の処理で生まれているのです。
初心者と上級者で変わる意識ポイント
「晩餐歌」のような繊細な曲を歌うとき、初心者と上級者では意識すべきポイントが少し変わってきます。
自分が今どのステージにいるかを把握し、それに合ったアプローチをすることが、上達への近道になります。
ここでは初心者と上級者それぞれに向けた意識のポイントを整理していきます。
初心者が意識すべき「力を抜くこと」
まず初心者の方にとって一番大切なのは、「頑張りすぎないこと」です。
どうしても「うまく歌おう」と力んでしまいがちですが、「晩餐歌」のような曲は、力を抜くことで初めて本当のニュアンスが出るタイプの楽曲です。
ピッチやリズムの細かいズレを恐れず、「歌詞をつぶやく」くらいの気持ちで歌い始めるのが、最初の一歩としてとても効果的です。
一回「話し声」くらいの脱力感を意識してあげると、それっぽく歌うことができます。
上級者が挑戦したい「間」と「ニュアンス」
一方、ある程度歌い慣れている方は、さらに踏み込んだ「間(ま)」と「ニュアンス」のコントロールに挑戦してみましょう。
語尾の息の量、震えるような不安定さを足すだけでも印象は大きく変わります。
「味気ない」で一度息を止め、「ないない〜」で再び息を流す。この技術が楽曲全体を飽きさせない要素になっています。
また、繰り返されるメロディの中でも、1回目と2回目でわずかに声色や息の表情を変えることで、深みが増します。
この「意図的なムラ」を作ることが、上級者に求められる表現技術です。
ZIGZAGミュージックでtuki.さんのような歌声を
ZIGZAGミュージックではtuki.さんの曲に特化したレッスンを行えます。
マンツーマンのレッスンで、一人ひとりにあったカリキュラムですすめていきましょう。
表現力やニュアンスを徹底的に磨きたい方には、ぴったりの環境です。
まとめーあなたもtuki.さんのような歌声をめざせる!
いかがだったでしょうか。
今回はtuki.さんの「晩餐歌」という楽曲を通して、歌詞・歌声・表現技術まで幅広く解説してきました。
「晩餐歌」の持つ独特な世界観は、シンプルでありながらとても深いものです。
初心者の方も、上級者の方も、まずは自然体でいられる声を探すところから始めてみてください。
そしてぜひ、tuki.さんのように「自分だけの晩餐歌」を歌い上げられるよう、ZIGZAGミュージックで日々の練習に取り組んでいきましょう!