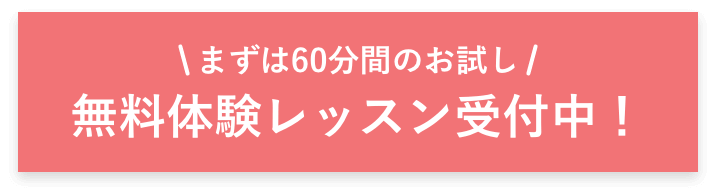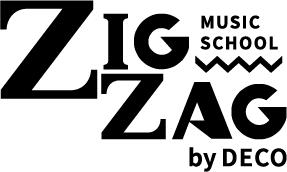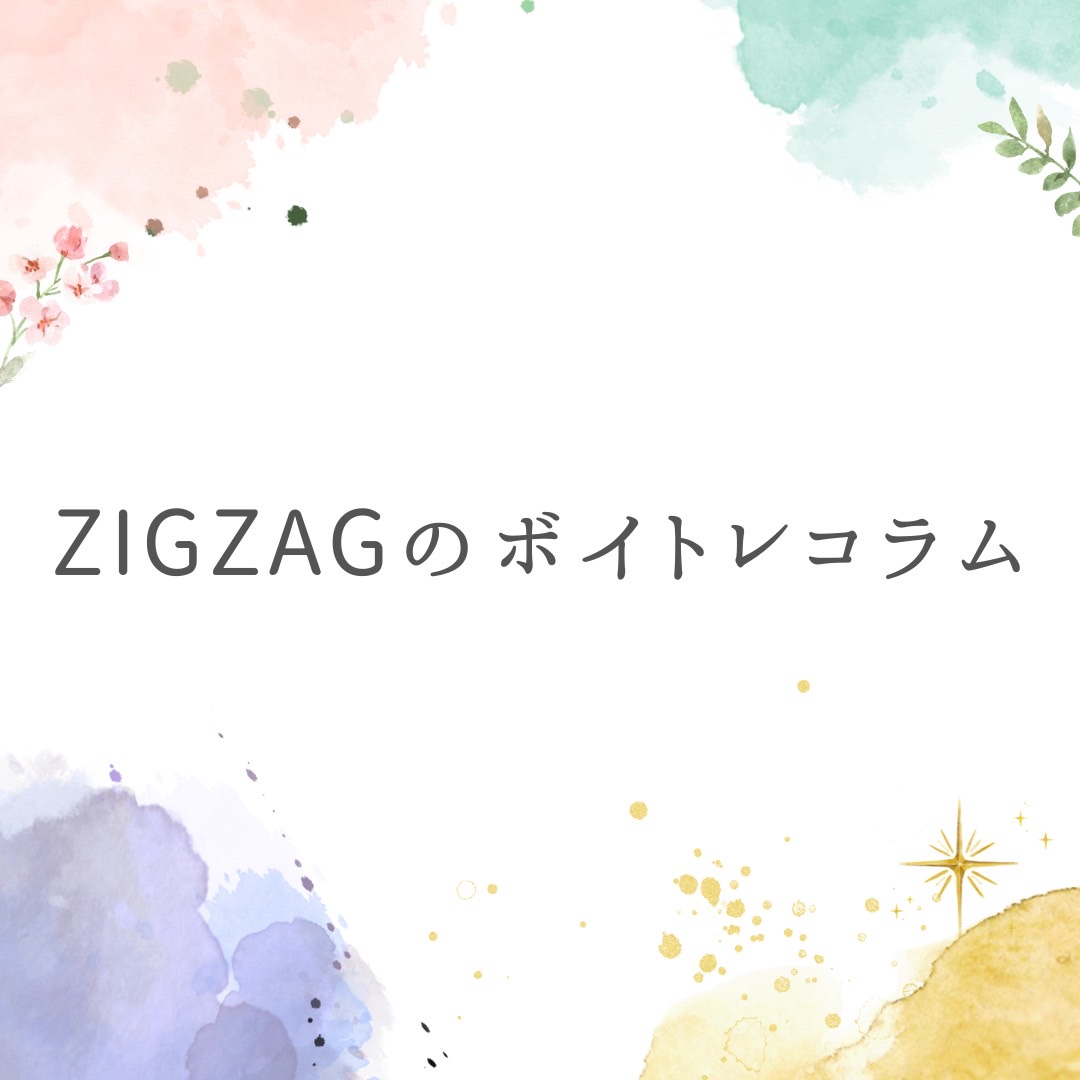日本独自の歌のジャンルだけれどもよく知らない・・・そんな人も今回読めばきっと演歌通になれること間違いなしです、それではいきましょう!
演歌が「独特」と言われる理由とは
演歌というジャンルをひとことで説明するのは、なかなか難しいものです。
特に初めて歌おうとする人が「難しい」と感じるのは、その独自のリズム感と歌唱スタイルがあるからではないでしょうか。
ここではまず、そういった演歌特有の歌い方をひもときながら、「なぜ難しそうに見えるのか?」の正体を見ていきたいと思います。
演歌特有の節回しとリズム感
演歌を聞くとうねりのある波打つようなメロディが印象に残ると思います。
これは「節回し」と呼ばれる民謡などによく見られるテクニックで、ただ音を伸ばすのではなく、微妙な揺れや抑揚、ドスの利いた響かせ方を含めて感情を乗せていく技術です。
ポップソングは基本的に「メロディライン」が揺れないように歌うことがいいとされていますが、その逆に積極的にメロディラインを揺らしたりうねらせたりするのが演歌の特徴といえます。
リズムに関しても演歌は単調なゆっくりのリズムの中で、そういった「節回し」を通して複雑なリズムなどをとっていきます。
これが洋楽などの「細かいリズムに乗るのが得意」という方でも、最初に戸惑ってしまう原因でもあります。
こぶしやビブラート
そして演歌といえば、「こぶし」と「ビブラート」です。
これらは単なる歌のテクニック以上に、演歌においては感情、情念を伝えるためのツールとなっています。
「う〜」と揺らす声には、聴く人に情景を感じさせる力があります。
ただやみくもに揺らすだけでは伝わらないので、歌詞を読み解いてどこで「いれるのか」「抜くのか」をしっかり判断してあげることが大事になります。
ヨナ抜き音階
演歌のメロディに他の音楽と違う感覚があるとしたら、それは「ヨナ抜き音階」と呼ばれる独特の音階が使われているからです。
「ヨナ抜き」とは、ドレミファソラシドの中から「ファ(4番目=ヨ)」と「シ(7番目=ナ)」を抜いた音階を指し、和風の響きを強く感じさせる構成になっています。
この音の通りみちには、歌詞の切なさや人間味を後押しする効果があります。
演歌を歌うときに、この音階の存在を意識しておくと、メロディラインの独特な動きや、間の取り方にも自然と説得力が生まれてきます。
ためしに鍵盤でこの音を鳴らして自由にうたってみましょう。
なんとなく演歌に聞こえるはずです!

プロ歌手に学ぶ演歌の表現技法
様々な演歌歌手がいますが「演歌の象徴」となっているのが、石川さゆりさんのようなベテラン演歌歌手です。
ここでは、石川さゆりさんを例にとりながら、上達へつなげるためのヒントを探ってみましょう。
石川さゆりの歌唱に見る「抑揚」の美学
石川さゆりさんの代表曲「天城越え」を聴くと、一音一音に込められた「間」と「抑揚」に心を奪われるはずです。
ただ音を伸ばしているのではなく、「言葉の余韻」をのこしながらゆらしたり、かと思えば力強く歌い上げたりします。
石川さゆりさんはこの「タイミングの操作」が絶妙です。
たとえば「天城越え」では
「隠しきれない 移り香が」
という部分の「し」「い」は両方とも声がフェードアウトするように抜けています。
しかし「い」のあとにかすかに声をのこしてビブラートで印象をのこしています。
また「くらくら燃える 火をくぐり」などの「燃える」では「も→お↑お→お↓える」といった形で「お」をうねらせてそこに情念を含ませます。
セリフのように語りかける瞬間があり、感情が高ぶるところで少しテンポを速め、また別の場面ではぐっと間を取る。
こうした「動きのある間」が、歌に表情を生み出しているのです。
顔と身体を使った情感表現とその影響力
演歌歌手のステージを見ていると、顔や身体の動きが非常に豊かであることに気づきます。
これは決して芝居がかっているわけではなく、むしろ「歌の一部」としての自然な所作になっているのです。
口角の動き、眉の上げ下げ、手の振り方ひとつが歌を震えさせるための秘訣になっていて、ポップスのようにまっすぐ立って歌うだけではその微妙な歌の揺れを表現できないことに気がつくでしょう。
つまり、演歌においては「表現」とは「声だけの問題」ではありません。
全身を使って感情を乗せていく。
それが、プロの演歌歌手が持つ圧倒的な説得力の正体です。
演歌を支える発声のヒミツ
演歌を歌ううえで、こぶしやビブラートといった技術ばかりに意識が向きがちですが、実はそれらを支える発声の基礎が整っていないと、どれだけ練習しても「演歌らしい響き」は出せません。
ここでは「演歌らしい」歌い方のための発声についてみていきましょう!
腹式呼吸で声に芯と安定をつける
演歌をしっかりと響かせるためには、腹式呼吸の習得が欠かせません。
特に演歌では歌い上げる技術も必要ですが、「ろうそくの火をゆらさない」ほどの細い息で響きをつくる必要があります。
こういった息の繊細な使い方ができるようになると声が薄い状態でのビブラートを長く出せるようになり、まさに「うまい演歌のうたいかた」ができるようになります。
そのためにはたくさんの息のコントロールができる腹式呼吸が欠かせないということですね。
喉に頼らない響きの感覚
「高音が苦しい」「こぶしがうまく回らない」といった悩みの多くは、喉に力が入りすぎていることに原因があります。
演歌を無理なく歌い続けるためには、喉で音を押し出すのではなく、「響かせる」意識がとても大切です。
喉を開き、リラックスした状態で声を出すには、ハミングやリップロールなどのウォーミングアップが効果的です。
とくにリップロールは、喉の余計な力を抜きながら、息の流れと声帯の連動感覚を鍛えることができる、非常に優れたトレーニングです。
この感覚がつかめるようになると、喉でがんばらなくても「体を使った響く声」が出るようになり、こぶしもビブラートもスムーズに乗るようになります。
口角まわりの筋肉で音程へアプローチ
演歌では、言葉の輪郭をはっきり伝えることが必要なため、ただ声を出すだけでなく、顔の筋肉を細かく使って音程やニュアンスを操る技術が求められます。
例えば、口をあけて歯をしまった状態で「あ」と発音してあげたあとに、歯ぐきをだして同じ言葉を言ってあげましょう。
すると歯茎が見えているときのほうが音が明るくなっていることに気づくかとおもいます。
演歌の「語りかけるような表現」には、この表情のニュアンスが必要不可欠であり、顔も発声の一部としてトレーニングする視点が欠かせません。
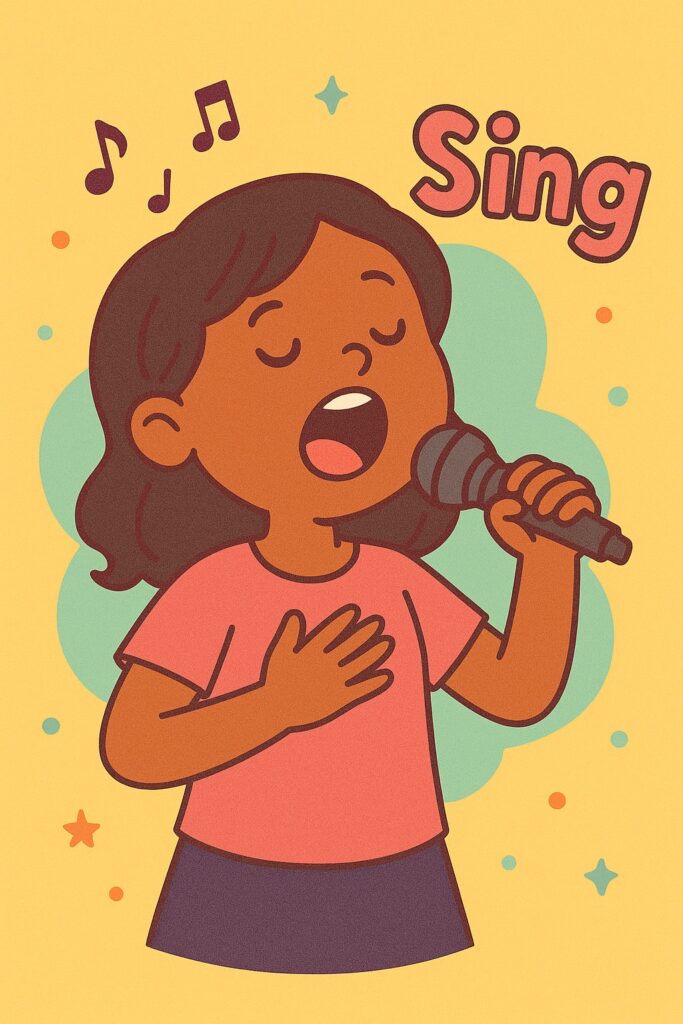
演歌がうまくなる練習メニュー
ここまで演歌の特徴や発声のヒミツについて見てきましたが、いざ実際に歌おうとすると「どうやって練習すればいいの?」という疑問が出てくると思います。
演歌は一朝一夕で身につくジャンルではありませんが、正しい順序で練習を重ねることで、誰でも確実に上達できる音楽でもあります。
ここでは「こぶし」「ウィスパーボイス」「ミックスボイス」の3つを軸に、実践的な練習方法を紹介していきます。
こぶしを習得するための段階的アプローチ
こぶしとは「声を揺らす」技術ですが、実際には音程を細かく上下させている状態です。
そのため、まずは音程の<なめらかな移動>に慣れる必要があります。
まずは「ド・ミ・ド」のような2音を、はっきりと分かれた状態で歌えるようになります。
その後、次第に2音をなめらかにつなぐように発音していってあげます。
「ド〜ミ〜ド〜」のような形です。
これができるようになったら、今度は「ド〜ミ〜レ〜ミ〜ド〜」のようなさらに音程差を入れて、リズムを取りながら練習していきます。
こういった基礎練習も大事ですね。
音の階段を滑らかに下りたり登ったりする感覚を覚えることから始めてみてください。
演歌で使われるウィスパーボイス
演歌ではウィスパーボイスのようなテクニックも使われます。
たとえば「天城越え」の
「なにがあっても もういいの」
などはウィスパーとミックスボイスのかけ合わさったような歌い方ですし
「隠しきれない 移り香が」
の終わりなどもきれいに声がフェードアウトされています。
こういった微妙な歌い方を取得するためには、しっかりとウィスパーボイスの練習などで声帯を自由に動かせる必要があります。
また地声からウィスパーにしていくといった練習も有効なので、練習の中になんどかそういったセクションを加えてあげるようにしましょう。
演歌に活かすミックスボイスと口腔共鳴
演歌を歌う中で、「高い音になると急に声が細くなる」「こぶしが乗らない」と感じることはありませんか?
その原因の一つが、地声と裏声の切り替えにギャップがあること。
ここで鍵になるのが「ミックスボイス」の考え方です。
ミックスボイスというとポップスや洋楽の技術という印象がありますが、演歌にも応用できる要素がたくさんあります。
特に、地声の芯を保ちつつ裏声の響きを含ませる発声法は、演歌の感情表現を豊かにしてくれる重要な技術なのです。
まずは地声をピアノのスケールに上げたり、裏声を下げていきながらミックスボイスの基本的な練習を行ってあげます。
大事なのは喉奥の開きです。
演歌では特に喉を開いている前に響く声が大事になります。
口腔共鳴も同時に鍛えてきちんと演歌で通用する歌声にしていきましょう
まとめ:正しいボイトレで演歌が歌える!
いかがだったでしょうか。
演歌というジャンルは、たしかに一筋縄ではいかない奥深さがあります。
でも、それは「できる人にしか歌えない」という壁ではありません。
むしろ、ひとつずつの気づきと積み重ねが、そのまま歌に表れていくジャンルなのです。
ZIGZAGミュージックでは演歌に使える歌い方を一人ひとりにあったレッスンカリキュラムで教えます。
まずは「なぜ演歌が難しいと感じるのか」を理解し、プロ歌手の歌い方から具体的なヒントを得て、基礎的な発声や身体の使い方を見直すこと。
そうすれば必ず演歌も上達していくでしょう。
ZIGZAGミュージックで理想の声を目指そう!
まずは無料体験レッスン から!