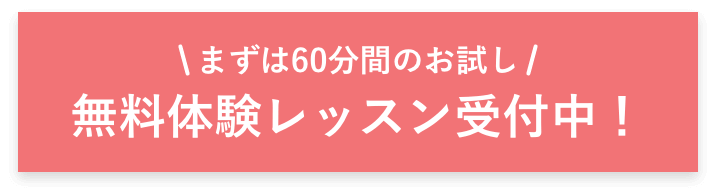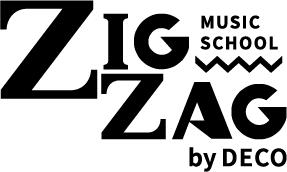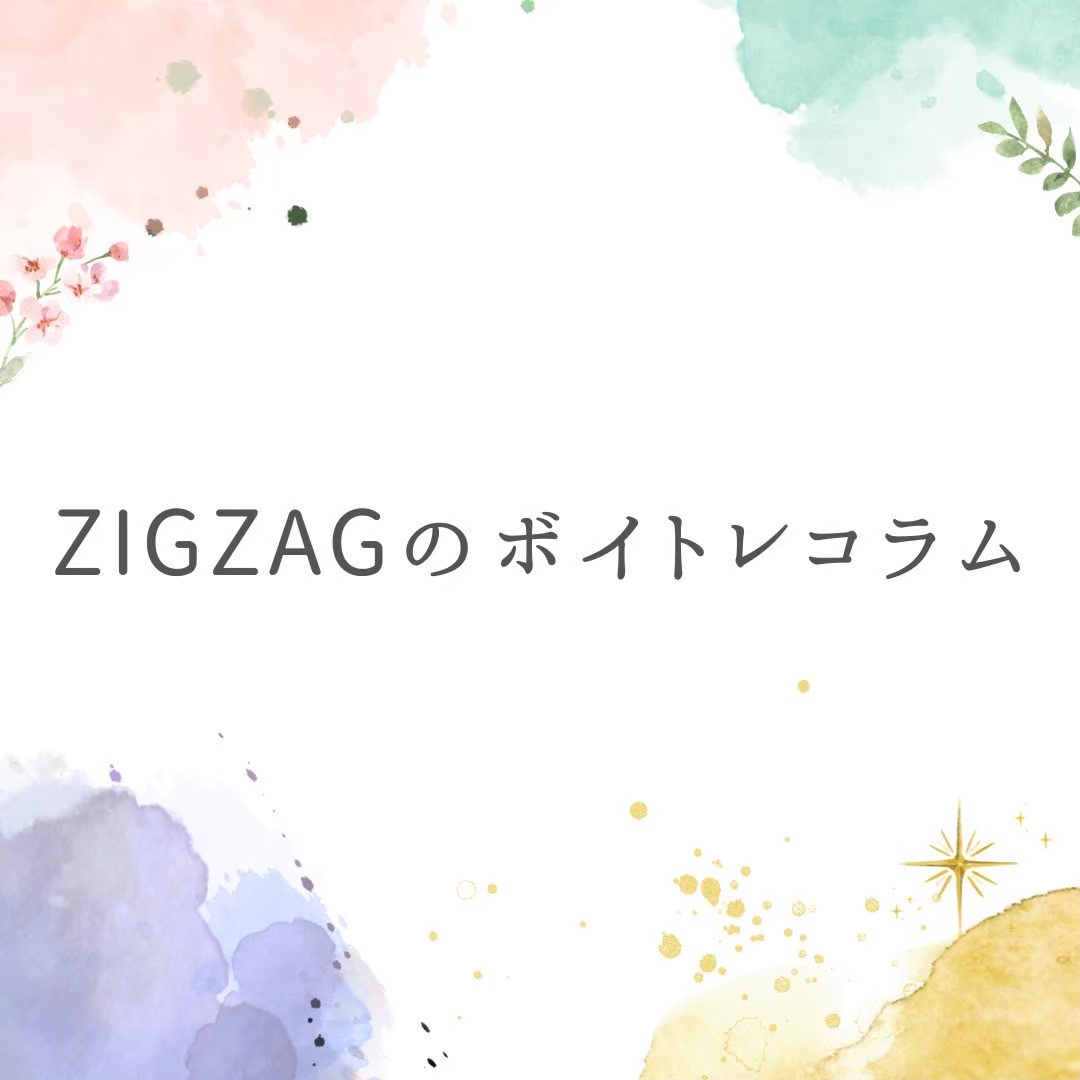「裏声が出せない・・・」「出そうとするとかすれてしまう」「地声との違いがよくわからない」そんな悩みを抱えている方、意外と多いのではないでしょうか?
ここでは、裏声の仕組みや種類の違い、出すための体の使い方から練習方法まで、段階的にわかりやすく紹介していきます。
それでは一緒にきれいな裏声を出せるようになっていきましょう!
裏声とは?基本的な仕組みと種類を知ろう
ひとくちに「裏声」といっても色々な種類があります。
歌の中でそういった様々な裏声を使い分けるのには、まずその仕組みや種類をしっかり理解しておくことがとても大切です。
声帯と音の関係性について知ることで、より精密な裏声のコントロールも可能になっていきます。
ここでは裏声と地声の仕組みの違い、そして裏声の種類について整理してみましょう。
裏声の仕組み
裏声とは、声帯が引き伸ばされて薄くなった状態で振動しているときの声のことを指します。
声帯が引き伸ばされると、振動の速度が上がり、高くて柔らかい音が出るようになります。
輪ゴムを強く引っ張って鳴らすと音が高くなる、そんな感覚に近いです。
実際には喉の奥にある筋肉が声帯を引っ張り、薄く保つことで裏声を出しています。
また、裏声は一般的に声帯の接触面が小さくなり、空気が漏れやすくなるため、息っぽく聞こえることが多いです。
トレーニングを積むことで息漏れコントロールし、しっかりと芯のある裏声も出せるようになっていきます。
裏声を出せるようになりたい方はこちら!地声の仕組み
一方、地声は声帯がしっかり閉じて振動している状態です。
振動の幅が広く、声帯同士がしっかりとぶつかっているため、太くて力強い声になります。
息の圧力にしっかり耐えられるため、歌詞を明瞭に届けやすく、話し声もこの声区で出すのが一般的です。
『「裏声」は高音でしか使われず、低音で使われる音はすべて地声だ』という誤解がありますが、裏声は実際には思ったよりも低音まで出すことができるので、その音が「芯」を持っているのか判別できるようになるのがもっとも大事だといえるでしょう。
裏声を使った様々な声
裏声と一口に言っても、実はその中にはいくつかの種類があります。
代表的なものが「ファルセット」「ヘッドボイス」「ミックスボイス」の3つです。
ファルセットは、空気が多く漏れる息っぽい裏声。
クラシック音楽やバラードで繊細な表現をしたいときによく使われます。
ヘッドボイスはファルセットよりも声帯がしっかり閉じ、息漏れの少ない、響きのある裏声です。
特に女性アーティストが多用する傾向があります。
そしてミックスボイスは、地声と裏声の中間のような声。
力強さと柔らかさを兼ね備えており、ポップスやロック、K-POPなど幅広いジャンルで使われています。
表現の幅が大きく広がり、声の魅力も一気に増していきます。
まずは「自分が今どの声を使っているか」を意識するところから始めてみましょう。

裏声を出すことのメリットとは?
裏声を出せるようになると、歌の幅がぐんと広がります。
ただ「高い声を出せる」だけではなく、実は地声にもよい影響があったり、表現力が豊かになったりと、たくさんのメリットがあるんです。
ここでは、その具体的な利点を一つずつ見ていきましょう。
高音を無理なく出せるようになる
多くの人が裏声を練習したいと考える理由のひとつが、「高音を楽に出したい」という願望ではないでしょうか。
高音というのは、声帯が引き伸ばされた状態(つまり裏声の状態)をベースに出す必要があります。
力をいれて無理に出そうとすると、喉に力が入りすぎて、声が割れたり、声帯をいためて枯れたりしてしまいますが、裏声をしっかり練習することで、声帯を伸ばした状態でも安定して音を出す感覚がつかめてきます。
すると、力を入れずに高音域でも無理なくスッと声が抜けるようになり、喉の負担も減るというわけです。
裏声を出せるようになりたい方はこちら!歌の表現力が広がる
最近のJ-POPや洋楽では、地声と裏声を行き来するような楽曲がとても増えています。
裏声を正しく使えるようになると、こういった曲を歌えるようになります。
無理に地声で通すと曲の抑揚がなくなってしまう部分でも、裏声を使って感情の強弱をつけることもできるようになるので、歌の「伝わり方」が大きく変わってきます。
つまりテクニックの幅が増えるということですね。
ファルセットでやさしく語りかけるように歌ったり、ミックスボイスでサビをぐっと盛り上げたりと、表現の選択肢が広がることで歌うことも楽しくなりますよ。
裏声トレーニングが地声にも良い影響を与える
実は裏声のトレーニングは、地声の発声にもいい影響を与えてくれます。
裏声を出すとき、特に大事なのは息の流れです。
この息の流れを意識できるようになると裏声はきれいに響いていくことになりますが、地声でも同じことがいえます。
地声と裏声の違いは声帯の状態の違いが主なので息の流れ自体はそこまでかわりません。
裏声でしっかりと息の流れを意識できるようになると、地声でもちゃんと響く声をつくっていくことができます。
まさに一石二鳥。
高音も出やすくなって、地声まで強くなるなんて、お得な話ですよね。

裏声が出ないときの主な原因
「裏声を出そうとしても出ない」「かすれてしまう」そんな経験あるかたもいるかもしれません。
実は裏声が出ない原因にはいくつかのパターンがあります。
多くは体の使い方や感覚の誤解に由来しています。
このセクションでは、よくある原因を整理しながら、対処のヒントをお伝えします。
喉や呼吸の使い方に問題がある
裏声を出すためには、喉だけでなく、呼吸のコントロールがとても重要です。
特に「腹式呼吸」だと、安定した発声につながり裏声が響きやすくなります。
肩や胸を大きく動かさず、お腹まわりがふわっと広がるような呼吸を意識してみてください。
それから裏声にアプローチしていくと簡単に出せる場合があります。
裏声に必要な感覚が育っていない
裏声は単に「高い声を出す」だけではなく、体の感覚を繊細に使う必要があります。
よく例えられるのが「背中のほうから声を出すような感覚」。
喉の前側だけで出そうとするのではなく、声が後ろから抜けていくようなイメージを持つと、うまくいくことがあります。
また、ユニークな表現ですが「平安貴族のようにしゃべる」という意識も効果的です。
やや気取った、裏に抜ける「ほほほ、マロは〜」というしゃべり方をすることで、喉に力を入れすぎずに裏声の感覚を掴みやすくなります。
この「感覚を育てる」というのは、すぐには難しいかもしれません。
でも、ちょっとした発声の真似からでも、そのきっかけは掴めることが多いのです。
いろいろな「例え」を調べて、裏声がでるまで地道にためしてみましょう。
無理な発声や力みで喉を締めている
頑張って裏声を出そうとすると、つい喉に力が入ってしまう。
これも非常によくある原因のひとつです。
特に、地声で無理に高音を出そうとしている人ほど、裏声に切り替えるときに力みが残ってしまい、結果として喉が締まり、声が詰まったようになります。
実は腹式呼吸でなくても裏声は出すことができます。
深呼吸をして吐くときに「ほぉ」とため息をつくようなイメージで裏声を出してみてください。
いい感じに脱力ができて、きれいに出すことができたりします。
裏声は「がんばって出す声」ではなく「通してあげる声」。
なるべく力を抜いて、息の通り道を確保することを意識してみてください。

裏声を出しやすくする練習方法
さあいよいよ、練習にはいっていきましょう。
ここでは初心者でも実践しやすい、裏声に特化した練習方法を紹介します。
リップロールで喉をゆるめる
リップロールとは、唇をプルプルと震わせながら声を出す練習です。
これを音階に合わせて行うことで、喉に余計な力を入れず、自然に息を流す感覚をつかむことができます。
リップロールをするときは、声を大きく出す必要はありません。
小さな音でも構わないので、唇の振動が安定するように息をコントロールしてみましょう。
なれないうちは音を出さずにただプルプル唇が鳴るように動かすだけで大丈夫です。
こうすることで喉周りの筋肉がほぐれ、裏声が出しやすい状態をつくることができます。
音階にあわせ、まずは息の流れをつかんでいきましょう。
ささやき声から裏声へアプローチ
いわゆる「ヒソヒソ声」とよばれるささやき声は声帯が震えていない状態です。
この状態から「はっはっは」と笑う、もしくは「え!?」とびっくりしてみると裏声へアプローチしやすくなります。
電話で「よそ行きの声」を出す感じですね。
あとはこの状態から上へ音をあげていきます。
ピアノの鍵盤などを使って、どこまで高い音が出るかためしてみましょう。
高い音が出るようになったら、滑らかにスライドして出せるかためしてみましょう。
「ホ」を使った裏声発声練習
最初から裏声がある程度出せる人は、「ホ」という発声をつかってどんどんトレーニングをかさねていきましょう。
裏声は「息の流れ」が命です。
息が止まってしまうと声が途切れ、喉に力が入り、うまく響きません。
そこで有効なのが「ホ」の発声で、裏声にアプローチをしていく方法です。
次第に高いところまで裏声をあげていってください。
音が出ない音域ではため息のマネをし、「はぁ」を「ホ」にかえるところからはじめましょう。
最初は弱々しい音でも構いません。
大事なのは息を止めないこと。
声と息が一体になって前に流れていく感覚をつかむことです。
ファルセットを練習したい人は特にこういった一音ずつ分離したスケールの練習をしていきましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
裏声というと「特別な人しか出せないもの」と思われがちですが、決してそうではありません。
仕組みを理解し、少しずつ練習を重ねれば、誰でも確実に裏声を出せるようになります。
今回紹介した練習法やプロの歌手の例を参考にしながら、自分の声の変化を楽しんでみてください。
それではまた!
吉祥寺のボイトレスクール「ZIGZAG MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!