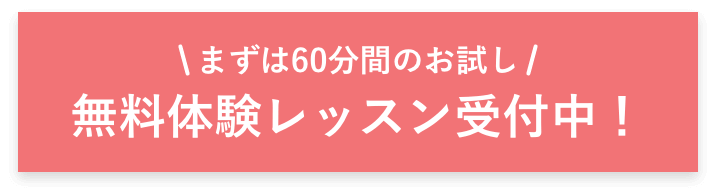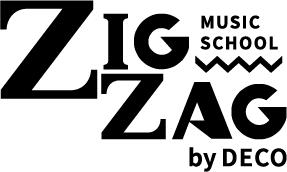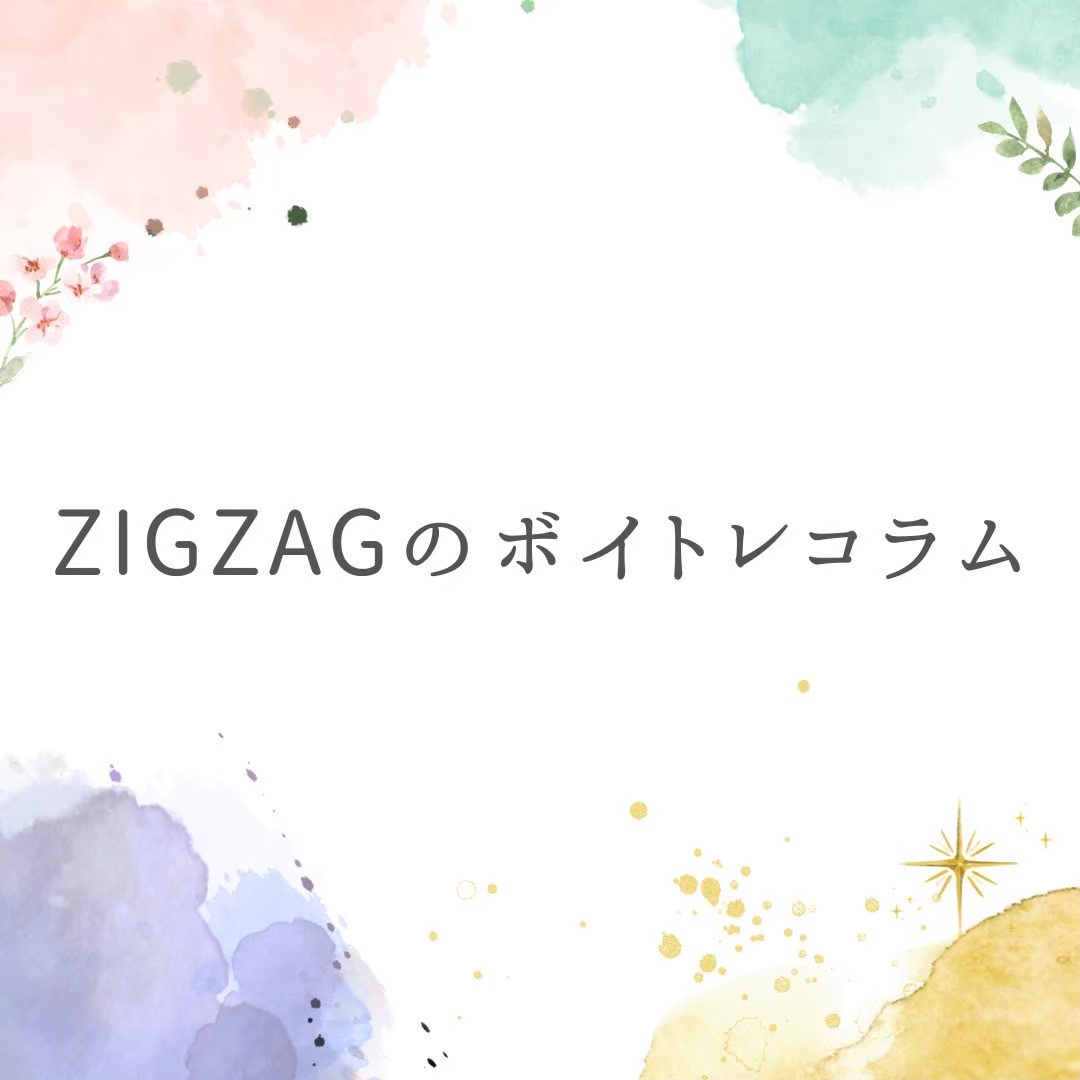巻き舌と聞くと、「自分には無理かも」と感じる方も多いかもしれません。
ですが実は、巻き舌は正しく練習すれば誰でも身につけられる発声トレーニングの一つ。
このコラムでは、巻き舌の仕組みやメリット、できない原因まで、ひとつずつ解説していきます。
巻き舌を習得するメリットとは?
巻き舌には発声改善につながる効果が多くあります。
ここでは、巻き舌がもたらす代表的なメリットを3つに分けて紹介します。
声帯まわりの筋肉が鍛えられる
巻き舌は、声帯やその周辺の筋肉を自然に動かすことで、喉だけに頼らない発声の感覚を養ってくれます。
とくに初心者にとっては、無理な喉声を避け、発声の基礎を整える助けになる重要なアプローチです。
また、巻き舌は舌先が震えることで、普段あまり使わない舌の筋肉が刺激され、発声全体に関わる筋力が活性化されます。
喉だけで声を出していた人が、体全体を使った声に変わっていくきっかけになることも多いです。
息の流れと共鳴感覚がつかめる
巻き舌は、息の流れで舌を振動させるテクニックです。
そのため、息の強さや方向、スピードなどを自然に意識できるようになります。
また、舌が振動することで口腔内や鼻腔に共鳴が生まれ、「響く声」や「通る声」の感覚もつかみやすくなります。
リップロール(唇をふるわせる)が発声練習でよく使われるのもこのためです。
実際、巻き舌ができるようになったことで、自分の声の響きが大きく変化したと感じる人も多くいます。
高音や滑舌への効果も期待できる
共鳴が高まり、口の中のスペースを使えるようになると、高音域の安定感が増します。
また、巻き舌の動きは滑舌にも影響を与えるため、「言葉がハッキリしない」といった悩みの改善にもつながります。
高音を出すとき、無理に声帯を締めるのではなく、共鳴のサポートを得ながら出すことで、喉に負担をかけずに安定した声が出せるようになります。
滑舌に関しても、舌先の柔軟性が高まることで、速いフレーズにも対応しやすくなるのです。
細かい歌の表現がうまくなる
巻き舌は単なる舌の運動にとどまらず、音のニュアンスやリズムのコントロールにも影響を与えます。
舌先の細やかな動きが鍛えられることで、歌の中での「語尾の処理」や「速いフレーズの粒立ち」がはっきりしてきます。
特に、演歌の細かい表現や、ジャズやロック、ラテン系の楽曲では、巻き舌のような細かな発音がノリやグルーヴ感を生み出す要素として活躍します。
巻き舌をできるようになりたい方はこちら!.jpeg)
巻き舌ができない理由とは?
「巻き舌に挑戦してみたけど、まったくできない」という方も多いと思います。
巻き舌ができないのには明確な理由があり、その多くはトレーニングで解決できるものです。
ここでは、巻き舌ができない原因を3つの視点から解説します。
舌の置く場所や癖によるハードル
まず1つ目の要因は、舌を置く場所が間違っているというものです。
下は上の前歯の裏辺りから、上の硬い口蓋のあたりに軽く触れるようにおきます。
コレが歯先においてあったり、または逆に口蓋の奥(喉に近いほう)に置きすぎるとなかなか震わせることができません。
日本語の発音習慣として舌を前後に大きく動かす機会が少ないため、筋肉がうまく使えないという背景もあるため、決して焦らなくて大丈夫ですが毎日少しずつ舌を付ける場所をかえながら練習してみましょう。
息の圧やタイミングが合っていない
巻き舌は、息の力で舌先を震わせるテクニックです。
舌の使い方だけでなく、「息の出し方」にも大きく左右されます。
重要なのは、舌先に当たる息の量・スピード・角度を微調整すること。
ストローを口でくわえて細く長く息を吐く練習なども、巻き舌のための息づくりにとても効果的です。
舌に力が入りすぎている状態
巻き舌ができない人の多くは、無意識のうちに「巻こう」と力んでしまっています。
特に舌の根元や顎にまで力が入ってしまうと、舌先がうまく自由に動かなくなってしまうのです。
脱力は巻き舌における最大のポイントのひとつです。
「舌はただおくだけ」という意識に切り替えるだけで、振動が起こりやすくなることもあります。
巻き舌をできるようになりたい方はこちら!
巻き舌を長く安定させるためのコツ
「一瞬だけできるけど、すぐ止まってしまう」そんな方は巻き舌ができる一歩手前、
ここでは巻き舌を安定させていくためのいくつかの重要なポイントをさらっていきましょう!
息のスピードと持続力を整える
巻き舌の持続時間を左右する最大の要因は、「吐き出す息の質」です。
勢いで一瞬だけ巻けても、息がブレたり切れたりすると、すぐに止まってしまいます。
理想は、細く長く、一定のスピードで吐く息。そのためにはブレスを整えるトレーニングが効果的です。
脱力と舌の位置を意識する
舌に力が入っていると、いくら息を送っても舌が跳ね返されて止まってしまいます。
重要なのは、舌は力を入れて動かすのではなく、「置いておく」こと。
上前歯の裏側に軽く舌先を当て、あとは息に任せてみましょう。
巻き舌が止まりやすい人は、「舌の置き場所」が定まっていないことも多いです。
最初はなれないかもしれませんが、舌の位置を安定させることで、振動の持続性もぐっと高まります。
口の形や顔まわりの筋肉も意識する
地味に見えて大きな効果があるのが、口のフォームです。
軽く「ウ」の形に口をすぼめて行うと、口腔内の空気圧が安定し、舌先の振動が続きやすくなります。
逆に「ア」や「イ」のように口を大きく開きすぎると、空気が逃げてしまい、舌先の振動が止まりやすくなるので注意しましょう。
口まわりの力もできるだけ抜き、リラックスした表情で行うのがコツです。
巻き舌トレーニングの具体的なやり方
さていよいよ実際のトレーニングを一緒にやっていきましょう!
腹式呼吸で脱力感をつくる
巻き舌をスムーズに行うためには、舌や喉、口まわりに余計な力が入っていない状態が必要です。
そのための第一歩が、「腹式呼吸によって全身の脱力感をつくること」です。
まずはイスに座り、膝を肩幅くらいに広げます。
その後に肘を前に出して、膝につくように身体を折り曲げます。
下を向いて息を吐き出し、鼻から吸い込むと、お腹が膨らむ感覚がわかると思います。
これが腹式呼吸です。
しばらくこの呼吸法に慣れた後は、巻き舌をためしてみましょう。
これだけでうまくいく人もいますが、歌う際は身体を起こして腹式呼吸をしなければなりません。
次第にトレーニングを通して、腹式呼吸の感覚に慣れていきましょう。
巻き舌の基礎練習
次に、実際に巻き舌の振動を起こす練習に入ります。
いきなり「巻こう」とせず、まずは息の力で舌を揺らすことを目標にしましょう。
口を「ウ」の形にすぼめる
舌先を上前歯の裏に軽く当てる
細く長く、一定の息を吐く
ここで「ルルル…」と舌が震える音が出れば成功です。
出ない場合も、舌や息の角度を少しずつ変えながら試してください。
音付きの音階練習と応用メニュー
舌が安定して震えるようになったら、今度はそこに音を乗せていきます。
「ルルルル〜♪」と声を出しながら、5トーンで練習してみましょう
このときの目的は「きれいな音を出すこと」ではなく、息・声・舌の連動感覚を育てることです。
無理に音程を合わせようとせず、自分の出しやすい音域で行って構いません。
巻き舌は、正しい練習を毎日コツコツ積み重ねることで、確実に習得できます。
焦らず、舌と息に向き合っていきましょう。
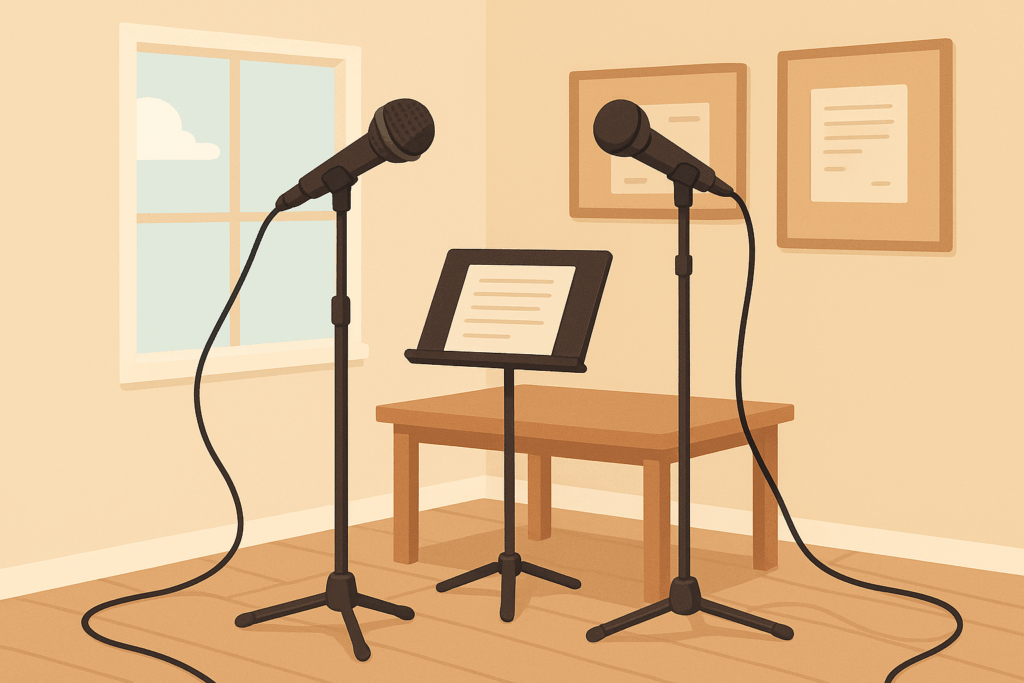
よくある質問(Q&A)
ここでは、巻き舌に関してよくいただく疑問をQ&A形式で簡潔に解説します。
トレーニング中の不安やつまずきにお役立てください。
Q1. 舌が短い人でも巻き舌はできるの?
A. できます。
舌の長さは多少影響するものの、重要なのは「舌の筋肉の柔軟性」と「息の当て方」です。
実際、舌が短めでも巻き舌ができるようになった人は多数います。継続的な練習で十分習得可能です。
Q2. 何歳からでも習得できますか?
A. 年齢は関係ありません。
舌の筋肉は何歳でも鍛え直すことができるため、10代でも50代でも、正しい練習を積めば巻き舌は習得可能です。
Q3. 巻き舌ができるようになるまでどれくらいかかりますか?
A. 個人差はありますが、早い人で1〜2週間、時間がかかる人で1〜2ヶ月程度が目安です。
習得のスピードは、練習の質と継続性によって大きく変わります。
Q4. 毎日どれくらい練習すれば効果が出ますか?
A. 最低でも「1日3分」から始めてみるのがオススメです。
大切なのは、時間の長さよりも「毎日続けること」
たとえ短くても、舌と息の連動に毎日触れていると、確実に感覚が育っていきます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
多くの発声上のヒントをくれるトレーニングです。
舌の柔軟性、息の流れ、共鳴の感覚など、声にとって重要なポイントを総合的に鍛えることができ、
その結果として、喉に頼らない自然で自由な声に近づくことができます。
難しそう?
いえいえ、まずはトライしてみましょう!
練習を続けることで、いままでにない発声を手に入れることができます。
吉祥寺のボイトレスクール「ZIGZAG MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!