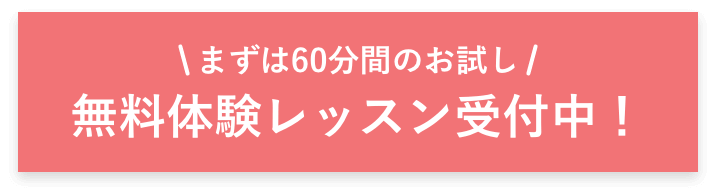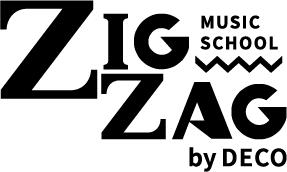男性が高音を出すのは難しい……そう感じていませんか?
僕自身、昔は「裏返る」「喉が痛くなる」「気合いで張り上げるしかない」といった状態で長年なやんでいました。
ところが正しい知識をつけた状態で練習をしたところ何年も悩んでいたことがどんどん解決できるようになっていったのです。
そこで感じたのは、正しい知識と練習さえあれば、男性も必ず高音を出せるようになるということ。
今回はその仕組みと改善方法を一緒に確認していきましょう。
男性が高音を出すのが苦手な理由
多くの男性が高音に苦手意識をもつのには、構造的な理由があります。
まずはその前提を知って、どういった練習が必要なのかを考えるきっかけにしていきましょう
声帯が厚い
男女の声の違いは「声帯の厚さ」によって生まれます。
男性の声帯は女性より太く長く、低音は安定しやすい一方で高音は出しにくい構造になっています。
これは輪ゴムを伸ばして鳴らした状態と、短くして鳴らした状態で音程が全然違うということからもわかるでしょう。
長さを短くしてゴムを分厚くすると、音は低くなり、逆に伸ばして薄くすると、音が高くなります。女性の声帯は男性よりも薄いため高い音が出しやすいのです
ただし、声帯は筋肉や粘膜でできているので、トレーニング次第で「伸ばす力」を育てることができるのがポイントです。
「生まれつきだからムリ」と思う必要はまったくありません。
女性のほうがもともと音感がある
一般的に女性のほうが音感が鋭いと言われることがあります。
実際に一過性誘発耳音響放射(TEOAE)という装置で測定された数値でも、男女間に音に対する敏感さの違いがあることが報告されています。
ただしこれはなにもトレーニングをしない状態での話です。
男性も練習をすることで同じ、またはそれ以上の敏感さを得ることができます。
音感は脳の神経回路を鍛えることで、確実に上達していくことができます。
普段の生活で高音を出すことになれていない
歌は響かせることに慣れること、そしてその感覚を覚えて使うものです。
日常生活で高い声を出す機会がほとんどない男性にとって、急に高音を歌うというのは感覚としてかなり大変なことです
ただし逆にいえば、練習の中で高音を響かせることになれていけば、出したいときに自在に出せるようになるということです。
高音が出したい方はこちら!
男性が高音を出すのに必要なこと
では、男性が高音を出すためには何を身につければいいのか。
男性が高音でつまずく最大の原因はバランスの悪い発声のまま力任せに声を出そうとしてしまうことです。
ここでは男性が高音を出すために大事なことをさらっていきましょう。
たくさんの呼吸を吸って呼気圧を作る
高音は息をたくさん吸って、適切な呼気圧と声帯の形を保つことで安定します。
これは笛を例にするとわかりやすいです。
笛を使って演奏をするとき、必要以上に強く吹いて息が多すぎると音はちゃんとなりませんし、逆に弱すぎても「ぴょろろ〜・・・」となさけない音がなるだけです。
腹式呼吸でしっかり呼吸が吸えていれば、息→声帯→共鳴という流れがスムーズになり、楽に高音へ移行できます。
声帯を適切に伸ばす
次に大事なのが声帯です。先程のはなしでいうとこちらは「笛」になります。
ただし声帯には笛と違って穴が空いていたりはしないので、指で塞いで高低差を出す代わりに、伸びたり縮んだり、厚くなったり薄くなったりして音程を調節していきます。
声帯を伸ばすためには喉周りの筋肉を鍛えることが必要です。
声帯そのものは自分では動けないので、それをコントロールする周りの筋肉をきたえてあげる必要があるからです。
ん?なんだか矛盾している気がしませんか?力んではいけないのに、筋肉を鍛える?
考えてもらいたいのはスポーツです。野球では足腰のいろいろなパートをきたえますが、実際にプレーをするときはその筋肉をすべて使うわけではありません。
むしろ脱力や力の入れ具合を意図的に抜いたりしながらパフォーマンスをあげていきます。
テニスでも「打つときは脱力してスナップをきかせて!」なんてことを聞きますね。
筋肉を鍛えるのは逆にリラックスをするためだということを知りましょう。
ただこの鍛える筋肉は、スポーツ同様何も考えずにつけていくだけでは効率よく鍛えていくことができません。
適切な指導をうけて行うようにしましょう
正しい響かせ方(ポジション)を把握すること
高音は「どこに響かせるか」「どう響かせるか」で音が劇的に変わります。
男性がやりがちな誤解は「力任せに上げようとする」ことだといいましたが、ここも同様です。
息と声帯で作った音を適切に響かせていくには共鳴を使って音を遠くに飛ばす必要があります。
響かせる方法としては
- 口腔という口の奥の響き
- 鼻腔という鼻の奥の響き
- その他(頭、胸など)
といった場所にひびかせていきます。
この「響かせ方」または「響きのポジション(位置)」を知るだけで、高音の力みが一気になくなります。
男性でも高い声が出したい方はこちら!
男性用高音トレーニング
ここからは実践編です。
「高音が苦手な男性」が今日から取り組めるトレーニングを、できるだけシンプルにまとめました。
腹式呼吸のトレーニング
高音を出すためには、まず 「息を吸える量」 がとても重要です。
息の量が少ないと声帯が押し戻され、どうしても力任せの高音になってしまいます。
まずはトレーニングで自然に呼吸が深くなるようにしていきましょう。
◆4カウントで吸う→4(8、12、16)カウントで吐く練習
こんなふうな感じで、息をたくさん吸って吐く練習をします。
腹式呼吸の感覚がわからない人は、仰向けになってしばらくするとお腹がふくらんでくるので、そんな形で腹式呼吸の感覚を掴んであげたあとに練習してみましょう。
これを慣れないうちは1日1セットでも効果があります。
腹圧を鍛える
高音を出す上では、ただ空気がたくさんあるだけではいけません。
適切に息の量をコントロールできるようになる必要があります。
腹圧は高音を支えるうえでとても重要なポイントです。
腹式呼吸ができるようになるとたくさんの息を吸うことはできるようになりますが、一方でコントロールする感覚がそれだけでは身につきません。
コントロールするためにはその息の圧力を適切にコントロールする必要があります。
「呼気圧」という表現をつかったのはそのためです。
◆腹圧でロングブレスの練習
しっかりとお腹の形をキープしたまま息を吐いていきます。
このと息の強さよりも、息が一定に吐けるかどうかを意識してあげてください。
まずは力を使わず息を出せるようになってからで大丈夫なので、次第に腹圧を使って安定した音が出せるようになっていきましょう。
口腔共鳴
高音を出す上で響かせられている感覚を覚えることは思った以上に重要です。
これは「口のどこへ響かせるか」や「顔の筋肉をどう使っているか」をその場で瞬時にコントロールする必要があるためです。
そういった試行錯誤をするためにも、口の空間がしっかりと空いた状態を作れるというのはとても大事です。
この空間を作るためには口をしっかり開け、舌、軟口蓋を適切に広げる必要があります。
これを口腔といいます。
口腔を広げるトレーニングには様々ありますが、主要なものは以下になります。
◆音階を使って上下に上げ下げする
「ま」や「は」やハミングで、しっかりと音がなるようにこころがけながら高いところまであげていけるようにしましょう!
Q&A
Q1:声が裏返ります。どうすればいいですか?
力みが強いと、声帯が適切に調節できず振動がなくなり、声が裏返りやすくなります。
深い呼吸→ハミング→軽くリラックスをして小さい声を出すなどをやってあげると次第によくなっていきます。
Q2:高音を出すと喉が痛くなります
痛みが出る時点でやり方が間違っています。
いったん中止し、ハミングやリップロールなど負担のない練習に戻しましょう。
Q3:最初は響いているのだが、高音を出そうとすると響きがなくなる
これは高音になるに従って力みが出ている証拠です。
まずはリップロール、ハミングなどで音がうえのほうまでしっかり出るように練習しましょう。
そのうえで脱力をすると高い声が楽に出るようになっていきます。
ただしあせりは禁物です。
Q4:声が重いので高音向きではない気がします
声質の重さ=高音が出ない、ではありません。
息・響き・裏声を整えれば、どんな声質でも高音は出せます。
Q5:どれくらい練習すれば高音は出るようになりますか?
どこからを高音とするかにもよりますが、音として高い音域を出せるようになるのは数カ月ですぐにできます。
そのあと響きを足していく作業が、色々な歌を歌えるようになるには必要です。
まとめ
男性でも高音は必ず出せるようになります。
重要なのは「喉で頑張るクセ」を手放し、呼吸・腹圧・響きの位置を整えていくこと。
今回紹介したトレーニングを続けることで、これまで苦しかった高音が驚くほど楽になっていきます。
焦らず、ひとつずつ練習していきましょう!
高音を出すための秘密はこちら!