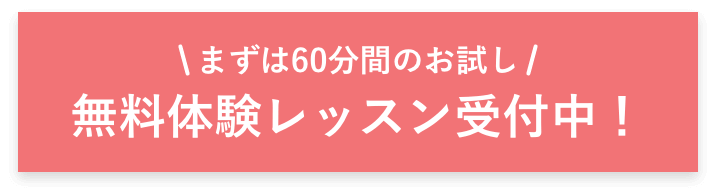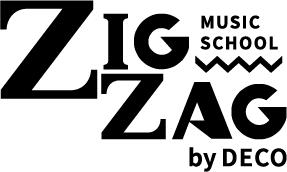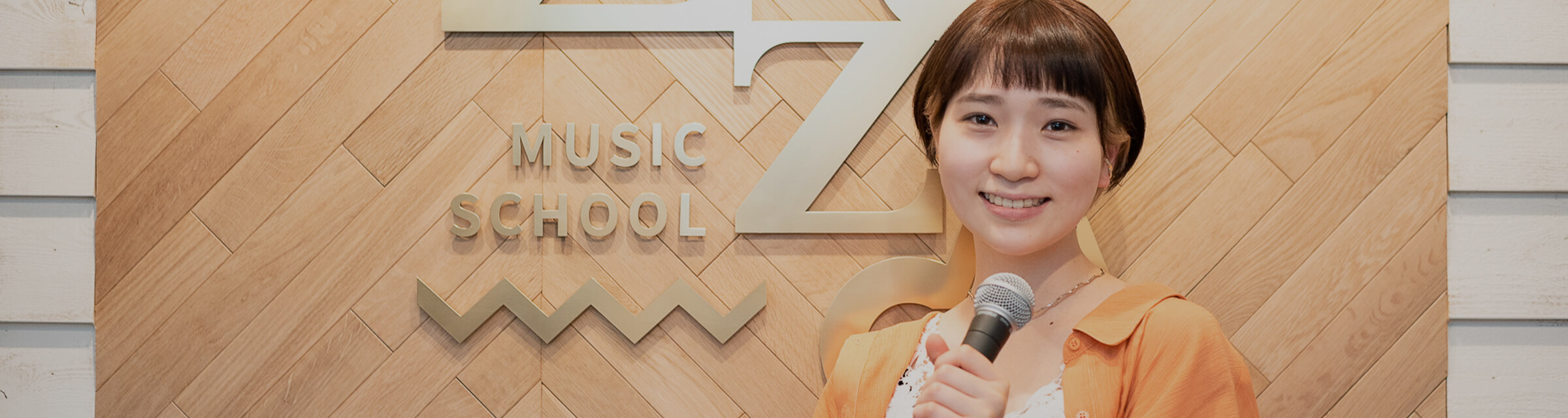地声
※ チェストボイス (胸声)

話し声に近く、太くて力強い声。
胸のあたりに響く感じがする。
声帯がしっかり閉じて振動しており、声に重みがある。
甲状披裂筋(TA筋)が主に使われる。
※ この筋肉が声帯を短く・厚くして、力強い音を作る。
強い倍音(高次倍音)を多く含む。
共鳴は胸や下方向に感じる。
声に芯があり、低〜中音域に適している。
裏声
※ ヘッドボイス (頭声)

軽やかで高く、柔らかい声。
頭の中や顔の上の方に響く感じ。
声帯の接触が地声に比べ浅く、空気が多く含まれることが多い。(特にファルセット)
主に輪状甲状筋(CT筋)が使われる。
※ 声帯を引き伸ばし、薄く・張る方向に働く。
芯のある裏声 = ヘッドボイス
声帯を開いた声、空気が漏れる裏声。息っぽく、軽い声 = ファルセット
という認識です。
声帯の主な動き
声は、声帯(声帯筋 + 声帯粘膜)が振動して空気を音に変えることで生まれます。
伸びる・縮む
ピッチ(音の高さ)を変える。
閉じる・開く
声の強さ・息漏れの有無を変える。
厚くなる・薄くなる
声質を変える(地声⇔裏声)
といった働きを主にしています。
共鳴とレジスターについて
発声は「音源(声帯)」と「共鳴体(声道)」の連動で成り立ちます。
レジスター(声区)とは、声帯の振動パターンの違い。
地声=モーダルレジスター
裏声=ファルセットレジスター
その音源を共鳴腔(喉、口、鼻)でどのように響かせるかで、声の聞こえ方が大きく変わります。
声帯振動モードについて
声帯の振動の仕方(振動モード)には、主に以下の4段階があります。
これは科学的研究で定義された分類(Titzeなど)で、特に発声教育や音声科学で使われます。
M0:パルスモード(低声帯振動)
いわゆる「うなり声」「しゃがれ声」など。
声帯が一部しか開かず、ブツブツと断続的に閉じたり開いたりする(例:デスボイス、咽頭語)。
M1:モーダルレジスター(地声)
通常の話し声や地声発声。
声帯が厚く、全体が振動。
TA筋の主導による発声。
M2:ファルセット・裏声モード
声帯が薄く、縁だけが振動する。
CT筋優位で、TA筋の関与が少ない。
息漏れが起きやすい。
M3:ホイッスルレジスター(超高音)
ソプラノや一部の男性シンガーの超高音域。
声帯がほぼ閉じず、極端に狭い部分が高速振動。
通常の共鳴とは異なる、笛のような音になる。
電気声門図とは
最近では、EGGという、声帯の接触面積の変化を電気的に計測する装置などがあります。
仕組み
喉の両側に電極をつけ、電流の通りやすさから声帯の閉じ具合を推定。
声帯が閉じていると電気がよく流れる(高い信号)。
開いていると電流が通りにくい(低い信号)。
何がわかる?
声帯の閉鎖時間・開放時間(閉鎖比)
地声か裏声かの判定(M1とM2の違い)
発声の安定性(振動が安定してるか)
実用例
声楽家のトレーニング分析
声優や歌手の声帯診断
音声合成・AI音声技術にも応用されている
すごい時代になりましたね。。
まとめ
地声と裏声の違いは
声帯の厚さ・閉鎖・使用筋肉の違い。
M1とM2はそれぞれ地声と裏声に対応し、その中間がミックス。
EGGや振動モード理論で、科学的に発声を分析・練習できる。
地声(M1)を安定させるトレーニング
TA筋を活性化、声帯の閉鎖を強める。
低音から中音をハミング(mm〜)で発声。
ネイザル音(ng)での発声練習(共鳴腔を保ちつつ閉鎖を意識)。
グロッタルアタック(声門閉鎖を意識)で「バッ」「グッ」「ゴッ」と出す。
※ 声門打撃
裏声(M2)を鍛えるトレーニング
CT筋の柔軟なコントロール、声帯の伸展力アップ。
[u](ウ)母音で息漏れ裏声(ファルセット)を滑らかに。
高音での「ホー」「ヒー」「ファー」など、軽い声で音程を上下。(f,hを混ぜる)
※ フェイクもあり
息漏れが少ないクリーンな裏声を出してみる(ピュアトーン化)。
最後に、いつも喉締め声になってしまう方へ。ミックスボイスを出してみたいのであれば、リップロールで好きな歌を歌ってみてください。少し理想に近付けるようになります。(声門上圧)
続きはレッスンで👋