こんちには、熊本昇真です。
今回のテーマは同期演奏になります。
アンサンブルにおいて生演奏では賄いきれない音を流すことを同期出しといいます。
例えば、ボーカル、ギター、ベース、ドラムの四人編成のバンドが、ピアノパートを含む楽曲を演奏する際に事前に録音したピアノ音源を再生しながら演奏することがあります。
全曲ピアノパートがある場合ピアニストを呼ぶというのも手ですが、一曲だけ(もっというとワンフレーズだけとか)ピアノが欲しいという場合は同期演奏が効率的でしょう。
マニュピレートともいい、マニュピレーターという専門職があるほど昨今ではポピュラーです。
今回はそんなあったらいいなを叶えるシステムについての解説になります。
クリックに合わせる場合と合わせない場合
まず初めにクリックに合わせてプレイしなければならない場合と合わせなくていい場合の紹介です。
クリックとはメトロノームのことで、
「音源とテンポが同期されたクリック」をメンバーが聴くことで同期演奏が可能になる場合。
アタックが弱いストリングスやシンセパッドなどはリズムを掴みにくいのでクリックを用意するといいでしょう。
逆に同期音源として鳴らしたいものがメインのリズム楽器の場合やオケそのもの(Voひとりのソロパフォーマンスの場合)、ハッキリとしたリズムが流れるので合わせることは容易で、その際クリックなどはいらないでしょう。
クリックが入らない場合大袈裟なシステムを組まなくても、オケCDでも対応可能です。
ただ、こだわればこだわるほどクオリティは上げられるためクリックが要らなくともこれから書く手法にも目を通すことをお勧めします!
クリックの利点
次にクリックを用意した同期演奏についてさらに掘り下げていきます。
リズム楽器さえずれなければ他のパートはそこに合わせて演奏が可能なので、クリックをきいてプレイするのは基本的にドラマーが多くなります。
ドラマーさえ同期音源に対してずれなければアンサンブルは安定するでしょう。
ドラムパートがお休みの時やカウント無しでいきなり全員揃って曲を開始したい時など、メンバー全員で同じクリックを共有して聞いている場合もあります。
システム1(MTRの場合)
ここからは同期演奏システムの作り方について解説していきます。
まず、MTR(マルチトラックレコーダー)の使用例。
昔ながらな手法かつシンプルで扱いやすくトラブルの少なさでいまだに支持されている同期システムです。
用意した音源データとその音源にピッタリ合うクリックデータの2つをMTRに入れ、PAorミキサーへ送るアウトプットから同期音源のみが鳴り、ドラマーが聴くためのイヤホンジャックならクリックだけが鳴るように設定して使用します。
ここで間違えてPA側にクリックが漏れてしまわないように、しっかり設定しましょう。
おすすめ機種はZOOM R8
-300x225.jpeg)
コンパクトで持ち運びも楽で電池駆動も可能。
複数の同期データを同時に再生でき、各フェーダーに割り当てられるのでパートごとの音量調整を現場で行える。
注意点としては、再生するデータのフォーマットが制限されます。
サンプリングレートは44.1khzか48khzのどちらかで、かつどちらも16bitで書き出された音源でなければ鳴らせません。
サンプリングレートがどちらかによってMTR本体の設定を変え合わせてあげる必要もあります。
自分は本体設定44.1で使っていたので使う音源データは44.1khz/16bitで書き出していました。
お手頃で便利なのですが、自由度は高いとは言えません。
例えば、複数のパートが同時に鳴っている同期の場合、楽器ごとに分けてPAに送れない(基本ステレオLとRの出力しかないため)、同期音源の事前準備でPC作業が必要(現場で急に変更したくてもPCがないとデータ自体の修正が難しい)など。
システム2(PCの場合)
次は自由度を高めた例です。
同期音源データの作成を行っていたPCをそのままライブにおける同期再生でも使用するという方法です。
PAに音を送るためにオーディオインターフェイスを用意する必要はありますが、データをMTRへ移す手間はなくその場で音源データの編集もダイレクトに行えます。
使用するオーディオインターフェイスの種類によっては、同期をパートごとに分けてPAに送ることも可能です。
例えばこのインターフェイスの場合、1&2からシンセサイザーをステレオで出し、3からサイドギターをモノラル、4からハモリのコーラスをモノラル、5から演奏者用のクリックを出力が可能。
ESI GIGAPORT ex
-225x300.jpeg)
それでもまだあまりがある!
パートを増やしても対応できます。
楽器ごとにPAに送ることで、その場所での最適な音量バランスをエンジニアが作りやすくなります。
(MTRでは各パートの音量を自分で変えることはできてもアウトプットが全てが一緒くたになったステレオのみで、PAによる介入が難しい)
あとMTRよりも音源データのフォーマットに制限がないので、より高音質な音源を鳴らすことが可能です。
より高音質で、現場のプロであるPAが音作りしやすい。
注意点は、PCスペック(低いと動作が安定しません)と自分の使用用途に応じたインターフェイスのチョイス&PCとの連携、設定の必要があるなど、ある程度の知識がいること。
逆にある程度PCおよびDAW、インターフェイスに慣れているならこちらの手法が自由度が高くお勧めです。
ソロパフォーマンスの場合でも、カラオケを流すよりすべての楽器をDAWに録音してインターフェイス経由でそれぞれのパートを独立してPAに送れば、バンドアンサンブルのようにその現場に適したバランスでミックスしてもらえるのでお勧め。
よりリアルなライブパフォーマンスができますよ。
それと同じ理屈でドラムを同期で流す際に、太鼓、シンバル類をそれぞれ分けて別々のアウトプットからPAに送ればその場でライブ仕様のドラムサウンドを作ってもらえるかもしれませんね。
まとめ
こんな感じで今回は同期演奏の種類と方法についてざっくり紹介しました。
ライブパフォーマンスにプラスαでさらに豪華に。あると嬉しい同期システムでした。
詳しいセッティングについては機種によって異なります。
また、どの機種を選んだらいいかわからないという質問も大歓迎です!
自分に合うシステムを構築してみましょう。
それではまた来月!
吉祥寺のボイトレスクール「ZIGZAG MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!
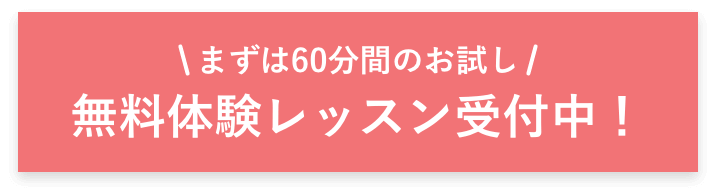
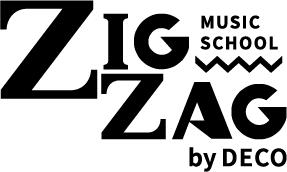
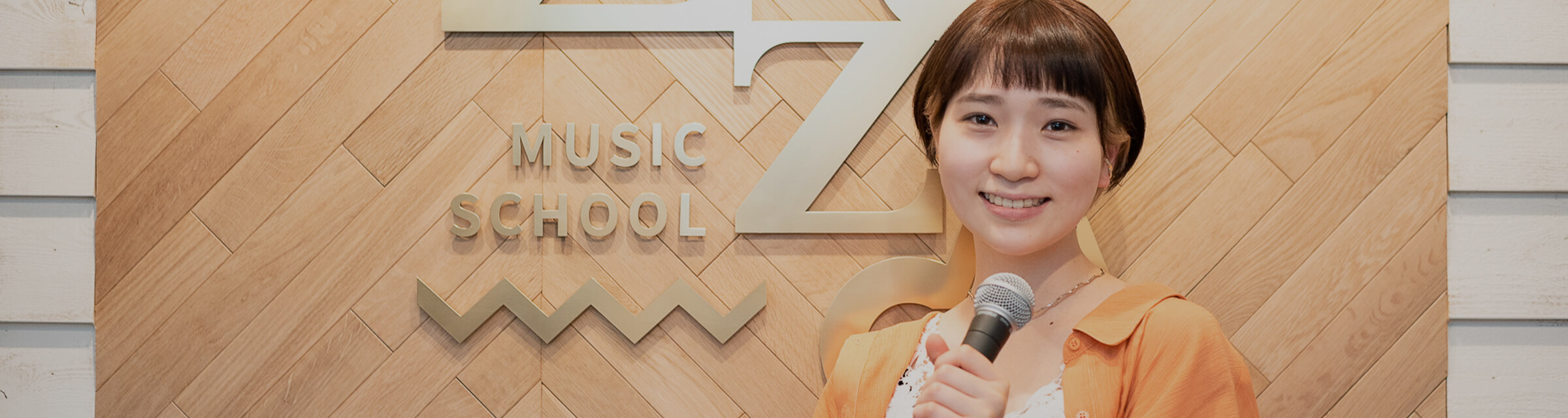


.jpeg)