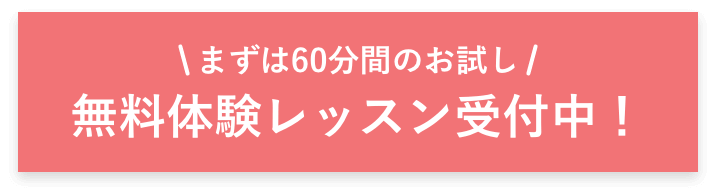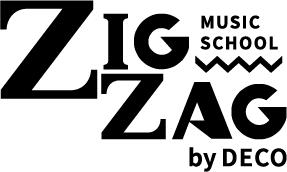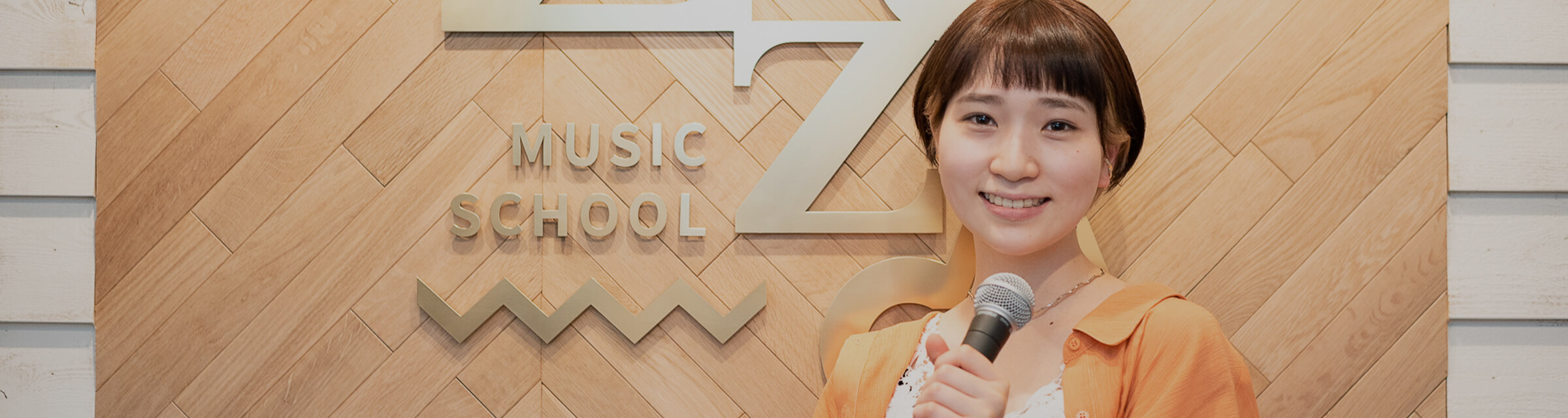こんにちは、ZIGZAGの岡です。
「自分は偽物なんじゃないか…?」
最近、「真正性(オーセンティシティ」という言葉について考える機会があって色々と調べていたので、勉強になった部分をここに一部まとめておきたいと思います。
とはいえこれから記載することは、あくまで考え方の一つだと思うので、「これがゆるぎない事実だ!」とは到底言えないですが、僕と同じような方向性でお困りの方のヒントになったら幸いです。
1. 創作の停滞は「自己への問い」から始まる
駆け出しの音楽家が突き当たる最大の壁、それは「自分が作っているものが本当に『本物』なのか?」という問いです。
この疑問に取り憑かれると、手が止まり、創作は停滞します。これは、あなたの創造性が次のレベルに進む前の、最も重要な自己確認のフェーズなのかもしれません。
そして、この「本物らしさ(オーセンティシティ)」の本質は、哲学でも、流行でもなく、あなた自身の「ルーツとの一貫性」にあります。というか、今回はその方向で考えてみたいと思います。
2. 「ルーツ」が科学的に意味するもの
ルーツとは、単なる過去の記憶ではありません。認知科学の観点から見ると、それはあなたの個人の知識基盤(Personal Knowledge Base)」であり、以下の要素の集合体です。
- 感情的記憶: 影響を受けた音楽、決定的な体験。
- 環境的知識: 育った文化、聴いてきた音、地域の歴史。
- スキルセット: これまでに身につけた技術と、その習得過程。
創造性の科学的定義は「新奇性と有用性の組み合わせ」です。あなたのルーツとは、この二つの要素を強力に結びつける、他者には絶対に入手不可能な「独自のフィルター」です。
• 新奇性(独自性)の源:
誰一人としてあなたと同じルーツを持つ人はいません。この独自の知識基盤をフル活用して「組み合わせ」を行うからこそ、結果として生まれる作品は他に類を見ない「新奇なもの」となります。
• 有用性(説得力)の担保:
ルーツに根ざした表現は、表面的な模倣ではなく、深い説得力と誠実さを伴います。聴き手は、作品にあなたの「本人の物語」を感じ取るとき、それを「本物」だと認識します。この誠実さこそが、作品の「有用性」や「適切性」を担保する核心かもしれません。
3. ルーツを見失った時の科学的再起動戦略
「本物らしさ」がルーツとの一貫性だと理解しても、実際に創作の手が止まってしまうのは、あなたの脳が「収束的思考」に支配されすぎているからです。つまり、評価(ジャッジ)が、生成(アイデア出し)を上回っている状態です。
創作を再起動し、ルーツに立ち返るためには、具体的な「行動」で脳をハックする必要があります。
【戦略 A:ルーツへの強制的な立ち返り】
まずは、自分の知識基盤を再認識することから始めましょう。
- ルーツの音源分析(インプット再構築): 自分の音楽人生で「決定的だった」と記憶している過去の音源を、理論的な分析を一切抜きにして、ただ感情のままに聴き直してみましょう。
その時、「なぜこの音に惹かれたのか?」「この音のどの要素が自分の琴線に触れたのか?」という感情的な記憶を再認識することが、表現の核を見つける第一歩です。
- 意図的な「制約」の導入: 自分のルーツと最も結びつきの強い要素(特定のコード、楽器、リズムなど)を、あえて「制約」として新しい曲に導入してみましょう。
他の新しい要素が無秩序になることを防ぎ、ルーツを通してフィルタリングされ、一貫性を保ちやすくなります。
【戦略 B:脳の疲労と偏りを解消する】
ルーツに立ち返るには、脳がクリアな状態である必要があります。
- 有酸素運動と「休憩」の活用: 手が止まったら、すぐにデスクを離れ、有酸素運動をしてみましょう。その場でマウンテンクライマーでも、スクワットでも構いません。運動は、創造的思考力を高めるだけでなく、凝り固まった思考の偏りを一時的にリセットします。
- 短い仮眠や「微睡(まどろみ)」の状態を意図的に作り出すことで、意識的なジャッジ(収束的思考)から解放され、ルーツからのインスピレーションが無意識下で結びつきやすくなります。
- フィードバックによる確認: 自分のルーツに根ざしたつもりでも、それが独りよがりになっていないかを確認するため、信頼できる第三者に作品を提示し、「この曲のどの部分に、あなたの個性(ルーツ)を感じるか」を尋ねるのもよいかもしれません。他者の視点を通じて、自分のルーツとの一貫性を客観的に確認することができます。このあたりは、僕ら講師を有効に活用してもらえるといいかもしれませんね。
というわけで、今回は真正性について簡単にまとめてみました。
それではまた次回に。
.jpeg)
カレー

アルバムを出しました。
吉祥寺のボイトレスクール「ZIGZAG MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!