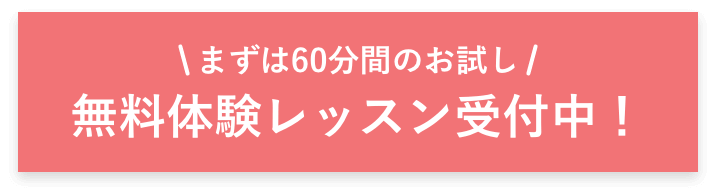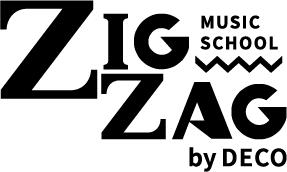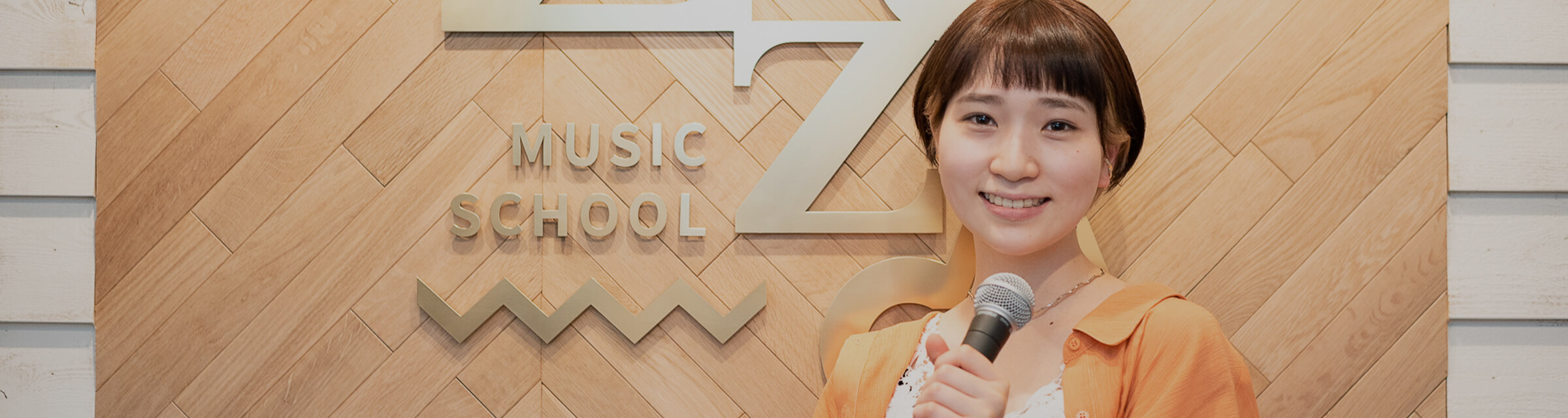私は自分が演奏するとき、常に心がけていることがあります。
それは、音楽を楽しむ心を忘れないことです。
簡単なことのように思えますが「もっと上手になりたい!」という気持ちが強くなれば強くなるほど、難しいことのように感じます。
特に子供時代は、自ら練習する癖がつくまでは大体親御さんが練習するよう促すため、親御さんにとっても子供にとってもギスギスしてしまうことがあると思います。
勉強はできるようになれば成績が良くなったり、良い学校に進学できたりと結果がついてきますが、音楽はできたところで「なんの意味があるの?」と思ったことが何度もありました。
そこで今回はそもそも「音楽ってなんで必要?」についてお話しします!
私はこれまでに、幼稚園で音楽講師を務めたり、障がいのある子供と音楽との関わり方について研究したりしてきました。
すこーしお堅い内容のように感じるかもしれませんが、私の経験も踏まえてお話しさせていただきます。
まずはじめに質問です!
まずはじめに皆さんにお聞きします。
みなさんは音楽の存在意義を考えたことがありますか?
なぜ教育現場で音楽の時間(授業)が存在するのでしょうか?
実はこれには明確な理由があります。色々あるのですが…^_^
今回はその色々ある中から2つ、挙げます。
それは「脳へのリラックス効果」「言語の壁を越える」です。
脳へのリラックス効果
これは、医学的にもちゃんと証明されています。
1例をここではお話ししますね。
最近日本で行われた実験なのですが、ある障がいのあるお喋りが苦手な子供たちに、音楽を聴いてもらう前と、聴いてもらった後の唾液を採取して唾液の分泌量を調べるという実験がありました。
唾液の分泌量からは、リラックス効果だったり、幸福度を調べることができます。
気になる実験結果では、音楽を聴いた後では聴く前より唾液の分泌量が増えていたんです。
これはほとんどの子供に同じ結果が見られました。
この結果から、音楽にはリラックス効果だったり幸福感を高めるといった作用があることが明らかになりました。
私たちが音楽を聴いたり演奏したりして良い気持ちになるのには、ちゃんと理由があったんですねー!
言語の壁を越える
これは、義務教育の現場で用いられる最新の指導要領に付け加えられた要素です。
私たちが生きる現代では、海外の方との交流は必要不可欠ですよね。
会話をするとなると、まず最初に「言語」を使いますが、言語が通じないとなれば音楽が世界と繋がる架け橋となる、と現在の音楽教育の場では考えられているようです。
確かに私自身、留学生や海外の友達と遊ぶ場合、なぜかほぼ毎回「カラオケ」に行って親交を深めておりました。
「あなたの国でもこの曲が流行っているの?」「あなたの国の今流行りの曲を教えてよ!」こんな会話からより仲が深まったような気がします。
そして驚いたのは、私の関わった海外の方はみんな、日本語の曲で発音が全然違っても大きな声でノリノリになって歌っていることでした。
ちゃんとした発音で歌わなければいけないという固定概念を持っていた私はその時カルチャーショックを受けました。
「別に完璧を求めなくたっていいんだ…!」と強く思った瞬間でした。
楽しむ気持ちを大切に…
今回は以上2点を挙げて「音楽ってなんで必要?」というテーマでお話しさせていただきました。
個人的に皆さんにお伝えしたい2点を取り上げたので偏りがある文章になってしまいましたが、今回のテーマで私がお伝えしたかったことは冒頭にもちょろっとお話しさせていただきましたが「音楽を奏でることを思いっきり楽しんでほしい」ということです。
自分のこれまでの音楽人生を振り返ってみると、上達するために一生懸命になりすぎて音楽が苦痛になってしまったり、外国語の曲に取り組む際、発音のことを気にしすぎて萎縮してしまったりしていました。
特に音楽高校、音楽大学に進学してからは、ある意味競争社会ですから、100点を取るために一生懸命になってしまい、その結果声が出なくなってしまったこともありました。
音楽とは本来100点なんて基準はどこにもないですし、上手に演奏するべきだ、なんて概念に囚われる必要がないものだと今の私は思います。
だから皆さんには過去の私のように萎縮せずに、音楽を楽しむ気持ちを忘れずに過ごしてくれたらな、と思います…